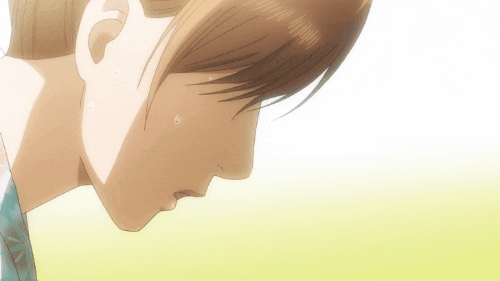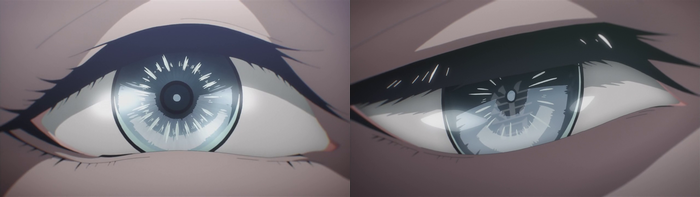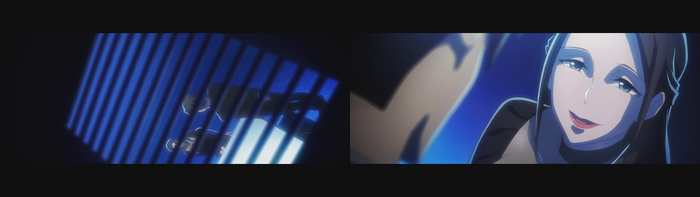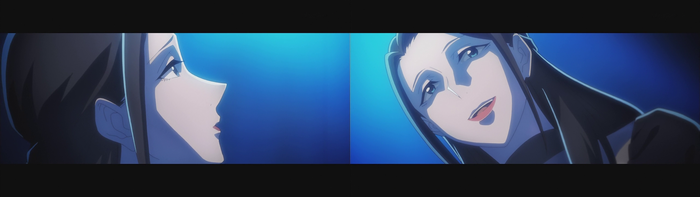詳しい素性はわからない。けれど、非の打ち所がないその実力はファンならだれでも知っている――それが木上益治という人だった。
監督を務めた『MUNTO』シリーズのDVD特典でオーディオコメンタリーに出演したり、メイキング映像に顔出しをしている以外、ほとんど露出がなく*1、京都アニメーションに来た経緯などをわずかに周辺のスタッフが話す程度で、多くは謎に包まれていた。
そこへスポットを当てたのが、「週刊女性」2019年10/22号(10/8発売)掲載の記事。専門学校時代から京都アニメーションに入社するまでの経緯を関係者に取材し、まとめたものだ。興味深い話ばかりだったが、個人的に気になったのはあにまる屋に所属していたときのプロレスに関する部分。
あにまる屋は別名“野獣屋”と呼ばれる、一風変わったアニメ会社で、毎日のように近くの寿司店で飲み会を開いていたという。
「普段は口数が少なくて黙々と仕事をする木上さんでしたが、酒は飲むほうでした。
アントニオ猪木やアニメの悪口を聞くと、暴力まではいかないけれども、ピュッと酒をかける(笑)。大友克洋さんと『AKIRA』の仕事をしたとき、絵にこだわる大友さんが殴られたという噂があってね。“だったら、あにまるの連中に違いない”という話になって、うちでは○○ということになって、木上の可能性は限りなくゼロだけど、真相は不明です(笑)」
みんなプロレス好きだったので、蔵前の国技館などに新日本プロレスの観戦に行くことも。社屋の大家さんに頼んで福利厚生施設としてスペースを借りトレーニング器具を置いて、身体を鍛えたこともあったという。
「木上くんは、筋トレはそれほどしなかったけれども、観戦は大好き。ある夜、真っ暗な会社に忘れ物を取りに戻った社員がいて、薄暗い中で彼がプロレスのビデオを見ていたそうですよ」(本多さん)
アニメの悪口を聞くと、酒をかける
木上益治のプロレス好きというトピックは、例えば京アニスタッフブログ「THE☆アニメバカ一代」でも書かれていて、人となりを知れるおもしろい趣味だなと思っていた。
ところで、八木さん。
私は初代タイガーのデビュー戦を81年に蔵前で観戦しました。
ああ、あまりにもなつかしい…
レンズ☆熱
ここで書かれている初代タイガーのデビュー戦とは1981年4月23日に蔵前国技館で行われた伝説のタイガーマスク vs ダイナマイト・キッド戦のことだ。また、この日のメインイベントがアントニオ猪木 vs スタン・ハンセンであり、それは「週刊女性」の記事で語られている『怪物くん』へと繋がる。
あにまる屋時代の先輩でいまもフリーで映画監督を続けている福冨博さん(69)も、木上さんのすごみを語る。
「画の線がきれいで、迷いがないのが特徴。『超人ロック』では僕が監督で、彼がレイアウターをやったんですが、画の直しはいっさいなかった。
『怪物くん』では原作にないプロレスのシーンを作って入れたけど、原作の藤子不二雄(A)さんからはまったくクレームもなかったですしね。
彼はもともと『バットマン』や『スパイダーマン』などのアメリカンコミックに憧れてこの世界に入ってきたようです。大人向けのものも描けるし、子ども向けも描ける、数少ない天才ですよ」
画の線がきれいで迷いがない
福冨監督が話されているプロレスシーンのある『怪物くん』で有名なのは1982年2月9日放送の125話「カミキル博士とハイタ氏(前篇)」だろう。このエピソードは劇画調のプロレスラーが多数登場する異色の話数として知られ、上述の猪木やハンセンをモデルにしたキャラクターも出てくるのだ(木上益治は原画でクレジットされており、プロレスシーンを担当したと思われる)。



アニメーター・木上益治の肉体的なアクション感覚の原点は、この辺りにある気がしてならない。 洗練されたアクションを描く一方、乱闘的なシーンを設計して賑わいのある画面を作る、というのも特徴のひとつではないかと思う。近年(京都アニメーション元請以降)の作品で関連する作品、パートをいくつか挙げてみると。
■『フルメタル・パニック? ふもっふ』(2003) 7話「 やりすぎのウォークライ」


■『けいおん!!』(2010) 4話「修学旅行!」

■『日常』(2011) 6話「日常の第六話」


実際の動きにどこまで手を入れているかは分からないものの、木上調とも呼べるタメツメ、タイミングがあることはたしか。プロレス技の応酬となった『日常』6話は、木上益治×プロレスの集大成的な話数。元々プロレスネタの多いマンガだが、プロレス好きの血が滾ったのか、アニメ版はより細かく描写されており、鹿へのジャーマン・スープレックスは背後を取る動きといい、ダイナミックさといい、非常に臨場感あるシーンに仕上がっている。さらに言えば、蔵前で観戦したという初代タイガーマスクのデビュー戦で、タイガーが決め技に使ったのが、ジャーマン・スープレックスホールドである。描くべきして描かれたという気もするから不思議だ。
そして、『怪物くん』のプロレスシーンに見られる(福冨流)回り込み+走り作画も、形を変えて受け継がれている。
■『たまこまーけっと』(2013) 9話「歌っちゃうんだ、恋の歌」

■『響け!ユーフォニアム』(2015) 12話「わたしのユーフォニアム」

この「上手くなりたい」と心の中で叫んで走り出す黄前久美子は、続けて「だれにも負けたくない」という気持ちを吐露する。それは木上益治にも通ずるものがあると思うのだ。
日本代表「白井健三」の床運動の演技に驚きました。
「シライ」と命名されるかもしれない「後方伸身宙返り4回ひねり」
人がこれほど高速の回転を人力のみで出来るものなのか?
私には何回ひねったのかどう回転したのかまるで確認できませんでした。
観る力が衰えたのか、体操選手の技術が進んだのか…
どちらにせよ作画出来そうもない。
意味不明な敗北感でテンション下がりぎみです。
シライ☆ひねり
三好は最近、仕事をしていて手元で進む仕事に違和感を抱くことがあります。
「これは私が描いた原画なの?…」と。
つまり、ぼんやりしていると、いつの間にか原画が上がっている…
今終わらせた仕事の過程が曖昧で、はっきりと思い出せない…
こういう症状で考えられるのは… ボケ… いやいや、そんな訳はない。
これはそう…昔、寝ている間に妖精が現れて代わりに仕事してくれないかなー、とか思ったことがあったけど、ちょうどそんな感じ…
ストレスが無くていいのだけど、でも何かおかしい。
勿論、遣り甲斐もあり充実しているのですが若い頃に感じた、バカみたいな衝動が希薄になっている… そのせいか?
何故だろうと考えた時に、あることに気が付きました。
これは技術を持った体が勝手に仕事をしているのだ、と。
体が私を蔑ろにしたことで心が仕事から離れてしまっているのだ、と。
これはまずい!
職人には絶対必要な「慣れ」あるいは「熟れ」ではありますが、気持ちの乗っていない仕事では観る人に伝わらない。
心底反省!
何とか主導権を体から取り戻して若かった頃のように「当たって砕けろ的創意工夫」を常に心掛け、仕事に向き合いたいと思います。
慣れ?☆ボケ?
『Free!』のハイカロリーな泳ぎや『無彩限のファントム・ワールド』のリンボーダンスにも顕著なように、文章からも様々な人体の動きを観察し、追及していることが窺い知れる。何より凄いのは、常に何かと戦い続け、技術向上を怠らないプロ意識とその姿勢だ。プロレスはそんな戦うアニメーターにとって、格好の相手だったのかもしれない。
今回はプロレスを切り口に追ってみたけれど、木上益治という人の仕事の、これはほんの一部だ。まだまだ、語られていない"覆面"があるはず。シンエイ、あにまる屋時代の作品から観直して、じっくりと確かめていきたい。